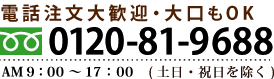1万個以上のさくらんぼの実が さくらんぼは桜のように最終的には大木に育ちますから剪定で樹の高さを制限、高くしないように作ります。生育年数で樹の大きさも違ってきますから、サクランボの樹は大きさによって実の着き方も選定のやり方で個性が出てきます。通常は成木1本から100kg前後実をつけます。 個数でいうと5千から1万個以上のさくらんぼが収穫できます。生産者は、脚立などを使い、ひとつひとつ丁寧に、実の色を確かめながら手で収穫していきます。 ...... 続きを読む
くだもの歳時記
全国一のさくらんぼ産地山形 山形県でさくらんぼの栽培が始まったのは、明治8年のことです。全国で育成が試みられる中、実らせることに成功したのは山形県とその周辺と北海道でした。 大きな要因となったのは気候でした。雨に弱いさくらんぼにとって、山に囲まれ空梅雨になることが多い山形の環境が非常に適していたのです。当時は生食での流通が難しかったことから、缶詰用の栽培が主流だったと言います 現在つくられている品種の最高峰は「...... 続きを読む
ラフランス 完熟サインとは ラフランスを美味しく食べるいちばん大事なことは「完熟を見極め」食べることです。ですからチェックポイントをしっかりおさえて完熟で召し上がってくれさえすればラフランスの本当の美味しさに辿り着くことでしょう。 完熟してからは冷蔵庫に入れると日持ちは伸びますが、ラフランスは食べ頃になってから美味しく食べられる期間は数日程度です。 [caption id="attachment_26220" ...... 続きを読む
ラフランスはフランス代表洋梨 ラ・フランスとは、1864年にフランスのクロード・ブランシェ(Claude Blanchet)が発見したフランス原産の洋ナシの品種です。 ラフランスは19世紀半ばにフランスでフランスを代表する品種として大きな期待を込めて生まれた洋梨を代表する品種です。 そのおいしさに「わが国を代表するにふさわしい果物である!」と賛美したことから「ラ・フランス」と名前がついたといわれています。 日本ではその名前に...... 続きを読む
ラフランス不人気の原因 実はラフランスは故郷である原産地フランスでは病害虫に弱く手間がかかることが原因して、ほとんど見られない品種となっているということが伝えられています。生産者に選ばれない品種、ほとんど絶滅寸前状態になっているといわれています。絶滅危惧種の存在になってしまったのです。 そんな中、1991年に山形県の「JAてんどう」がラフランスの原産国であるフランスに「ラフランスの苗木を1000本」贈呈しました。 ...... 続きを読む
ラフランスはフランス原産 ラフランスは19世紀半ば1864年にフランスでフランスを代表する品種として大きな期待を込めて生まれた洋梨を代表する品種です。そのおいしさに「わが国を代表するにふさわしい果物である!」と賛美したことから「ラ・フランス」と名前がついたといわれています。とてもフランスらしいお話です。 ▼山形県西...... 続きを読む
ラフランス生産量 栽培面積1位 山形県は、西洋なしの生産量が全国1位で全国の生産量の6割以上を占めています(令和2年)。特に、西洋なしの品種「ラ・フランス」は緻密な果肉、果汁の多さ、特有の芳香、そしておいしさから「果物の女王」と称されています。 山形県は全国の洋なし生産量は約1万9千トン余り、全国シェアで65%になり断トツの1位です。全国洋なし品種別作付け面積でもラフランスは洋なしの約65%の栽培面積を誇っています。 ...... 続きを読む
ラフランスの旬は11月 12月 ラフランスの旬は10月中旬頃から12月頃まで。山形では11月頃が出荷の最盛期になります。そして、お歳暮シーズンの年末まで最盛期は続きますからラフランスの旬は11月、12月ということになり翌1月まで供給が可能になります。それは冷蔵庫を使って温度調整により出荷日を決めて1月まで出荷量のコントロールをしながら続けていきます。 ラフランスは、完熟しないと美味しくない果物です。そのために主産地の山形県ではでんぷん濃...... 続きを読む
黒豆のおいしさ育てる風土 ここ丹波篠山は内陸型の盆地になっています。その特有の地形が寒暖差を生み、黒豆に甘みを与え、早朝の深い霧が、しっかりと潤いを与えます。 粘土質の保水力の高い土壌は、ミネラルや栄養分を多く蓄え、 さらに清らかな空気と水と美しい自然に恵まれ、美味しい豆を耕作するのに最適な土地なのです。この土地の代々の生産者は土作りを続けながらより美味しい丹波黒を求めて努力を惜しみませんでした。 フランスの有...... 続きを読む
丹波の黒豆 煮豆に美味しさ 丹波黒は枝豆としてよりもお正月の煮豆の黒豆としての存在のほうが有名な黒豆です。なんといっても煮豆の美味しさとそのふっくらした柔らかな食感、そして豆の大きさに存在感があります。 だだちゃ豆はプレミアムな枝豆として全国的に知られるようになりましたが、その違いとは何でしょうか。一緒に見ていきましょう。丹波黒は丹波黒豆枝豆としてよりは、お正月に食べる黒豆の煮物としてのほうが全国的に知られている黒大豆といえます。黒...... 続きを読む
枝豆との違いは何か 枝豆とは何か言えば、夏には欠かせないおつまみ。ごはんのお友ではないのに、夏の定番。ビール好きにはたまらないモノかもしれません。 「枝豆」とは大豆の未成熟の豆のことを指し、葉っぱの色が緑から茶色になるまで完熟すると大豆になります。この大豆は保存できる水分まで乾燥させますから、そのころには全く枝豆のイメージは無くなります。 大豆をが熟す前の緑色の状態のときに収穫したものが枝豆...... 続きを読む
青肉メロン 赤肉メロンとは メロンは果肉の色味から「赤肉メロン」「青肉メロン」に大きく二分されます。果肉がオレンジ色をしているのが「赤肉メロン」です。赤肉メロンは一般的に、コクのある強い甘みと芳醇な香りが特徴。完熟前でも青臭い香りは少ないです。果肉が柔らかめな品種も多いです。 メロンには夕張メロン、クインシーのようなオレンジ色の果肉の赤肉系メロンの品種やマスクメロン(アールス)アンデス、のような淡いグリーンをした果肉の青肉系メロンの品種...... 続きを読む
佐藤錦の初結実から100年 さくらんぼ佐藤錦の誕生まで、佐藤錦の生みの親である佐藤栄助氏は、大正元年(1912年)果肉は甘いが柔らく保存性が低く日持ちが悪く保存性の低い黄玉(きだま)と酸味は強いが果肉が硬く日持ちするナポレオンを交配し研究と選抜育成を重ね、大正11年に初結実を実現します。 佐藤栄助氏と共に新品種の開発に情熱を注いできた栄助氏の友人、苗木商を営む岡田東作氏((株)天香園の創業者)はこの新品種の将来性を見抜き...... 続きを読む
さくらんぼの種から芽は出るが さくらんぼの種から芽は出ることもありますが、さくらんぼは発芽率が悪いので、種を植えても芽が出る確率はかなり低く芽が出たとしても病気の抵抗性が低いため成木までの栽培は難しいようです。特に実を着けるようになるまで木が育つかというと否定的な言葉しか出てきません。 何故かというと、さくらんぼの木は病気に強く育ちの早いサクラの品種の木に接木して育てます。その根のある土台になる木のことを台木(だいぎ)といいますが、桜の...... 続きを読む
さくらんぼの生産量はどれくらい? 日本国内のさくらんぼの生産量は、ここ10年間平均で、18,300t程度です。山形県では、日本全体の約4分の3にあたる13,800t程度のさくらんぼの生産をしており、日本一のさくらんぼ産地となっています。 生食専用の品種、佐藤錦の特長は、見た目がきれいな鮮紅色で光沢もあること。甘みが多く、果皮が比較的厚くて遠地輸送にも耐え、さらに収量が安定していることなどです。 とにかく...... 続きを読む
さくらんぼの樹から何個のさくらんぼ? 樹の大きさによっても違いますが、成木1本からは5千から1万個のさくらんぼが収穫できます。生産者の方は、脚立などを使い、ひとつひとつ丁寧に、手で収穫していきます。 元々もっとたくさんの実がつきますが、実を大きくするために芽が出たころ(2月、3月頃)に芽欠きといって芽の数を減らす作業をします。 また、実がついたころに余計に着いた実は摘果といって実の数を減らします。いずれ...... 続きを読む
デラウェアの美味しさ特徴とは デラウェアの味は小粒だけども味は濃厚で特有の香りもあり美味しいぶどうといえます。デラウェアがほんとに大粒だったら申し分ないものと思ったものですが・・・。 本来というか、大粒ブドウの巨峰が出回る以前は、デラウェアがブドウ主流でした。ブドウといえばデラウェアという時代もあったのです。暑い夏の盛りに出回ります。お盆の頃が旬の夏ブドウの代表といえます。 昔は良く食べていたデラウ...... 続きを読む
日本ぶどう品種改良の変遷 日本のブドウの普及は、多くの品種が海外 から導入・試作された明治時代から本格的に始まりました。米国や欧州からの品種が持ち込まれました。しかし、降雨が多い日本では雨の少ない所で栽培される欧州ブドウの栽培は困難でした。 明治時代に普及に成功した品種の多くは栽培が容易な「キャンベルアー リー」「デラウェア」「ナイアガラ」「コンコード」 などの米国ブドウでした。 その後、明治末...... 続きを読む
全国的に見る産地 山形ブドウ ぶどうは全国で広く生産されています。日本全体の収穫量は年間17万6,100トン(2017年)で、都道府県別の収穫量では1位が山梨県。そして、2位長野県、3位山形県、岡山県と続き、この4県で約6割を占めます。生産量日本一の山梨県では甲府盆地を中心とした水はけのよい地域での生産が盛んです。年間の日照時間が長く、降水量が少ないという内陸性気候がぶどう作りに適しているのです。 山梨県、長野県に次いでぶどうの生産量全...... 続きを読む
シャインマスカット誕生秘話 ブドウは果皮の色で黄緑、赤、黒に分けられます。ぶどうには欧州種と米国種という系統による分類がありますが、ここでは色味、黄緑系、赤系、黒系で分類し、それぞれの代表的な品種を紹介しましょう。色の違いはアントシアニンという色素の蓄積の違いによるものです。 近年の気象の変化、特に地球温暖化によってブドウ栽培にも危機が訪れているといわれます。それは、温暖化によってもたらされる最低気温の上昇です。この問題は意外に大きな影...... 続きを読む