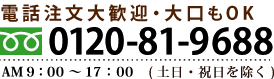純米吟醸「好好爺」のテイスト 白麹仕込みの純米吟醸酒が遂に誕生しました。日本酒のテイスト革命です。白麹は焼酎造りに使われていたもの、元々は黒麹の突然変異でできたものです。 白ワインのような日本酒 柑橘系の香りその心地よい酸味による独特のフレーバーは、上質の白ワインを彷彿させます。香りは柑橘の爽やかな香りに続いて甘い香りが漂います。 グラスに注ぐと一見は白ワイン、薄いイエローの色合いです。香りは爽やかな柑橘系の香...... 続きを読む
くだもの歳時記
スムージーのような粒々の果肉感 特徴はドロドロとした抜群のスムージーの果肉感と、ニンジンの自然な甘み。1000mlのニンジンジュースに使うニンジンの量は約1kg。すりおろし製法でニンジンが持つ食物繊維をそのまま味わえる飲み心地に仕上げています。 さらに、リンゴ果汁(山形県・青森県産)とレモン(愛媛県産)、梅エキス(国内産)を加えることで、とってもスッキリとした味わいに。にんじん嫌いな子供でもゴクゴク飲める魔法のにんじんジ...... 続きを読む
蜜リンゴと洋なしをワイン製法で 近年になって、コロナ禍の影響もあってか果物を使ったリキュールが人気を博してきています。しかし、その多くがフルーツ果汁にアルコール添加する製造方法が果実リキュールの大多数という状況にになっている現状があり、くだもの酒のファンの一人として少し残念なところを感じます。 安全性とか、製造方法に違法性とかの顕著な問題は全くありません。それはそれで合法的であり、お客様も問題なく購買している状況や人気も...... 続きを読む
シードルの美味しさと楽しみ方 洋なしスパークリングといわれるシードルポワレは、搾りたての洋梨100%でつくられるスパークリング果実酒になります。果実の味と香り溢れる清涼な味わいと、軽やかな飲み口を楽しめるのが魅力です。 ALCも2%から9%ぐらいまでで、甘味料や酸味料は一切加えていない自然の味わい。キリッと冷やしたポワレは、ディップやデザート、魚介、豚・鳥肉料理ともピッタリ、ブリヤサバランなどのフレッシュチーズと合わせると感動の味になるといいます。 ...... 続きを読む
洋なし100%原料の発泡酒 洋ナシの発泡酒スパークリングワインのシードルポワレとはフランスフランス北西部ノルマンディー地方ではシードル(りんごの発泡酒)と同じくらい親しまれている洋ナシ100%で作る発泡酒です。色は淡黄色から黄金色、ポワレ用の特別な洋梨を発酵させて造ります。 洋梨の発泡酒シードル、またの名をシードル・ポワレとも言います。洋梨の天然果汁を100%使用したシードルの一種だということなのですが、あまり知られていないのも事実です...... 続きを読む
吟醸酒スパークリング 月山物語 山形県産「雪若丸」を55%削りに仕上げた白いビーズの原料米で麹づくり。フルーティーで酸味を立てたキリッと飲み飽きしない女性にも飲みやすい発泡の吟醸酒です。ワイングラスに注いでおしゃれに食卓に輝きがまします。山形生まれの自然と蔵に生き続ける微生物が醸し出す発酵の力。和食にも洋食にも合わせることができます。 きっと食卓に花を咲かせる1本になりそう。ご家庭での食中酒としてどんな料理にも相性の良い独特...... 続きを読む
蜜りんごの美味しさ乗せシードル リンゴや洋なしのシードルの歴史はワインと同じくらい古く、ヨーロッパでは紀元前からシードル造りがおこなわれていました。4世紀ごろには、ローマでシードルを意味する単語が使われるようになり、9世紀にスペインにおいて、りんごのお酒を意味するものとして定着します。 さて、この度の「蜜りんごシードル」は蜜入りリンゴの究極品種といわれる品種「こうとく100%原料」です。天童市の阿部りんご園の生産した特有の香りの高さ、爽...... 続きを読む
あんぽ 柿干し柿の保存方法 あんぽ柿の保存方法は干し柿と同じです。ただし、しっかり乾燥して水分が抜けた干し柿よりも水分が50%と多いので、扱う際には表面を傷つけないように注意するようにしましょう。 干し柿の保存方法についてこ紹介します。今回は、常温・冷蔵・冷凍の3つの温度帯別に保存方法と保存期間をまとめています。あんぽ柿は水分50%、一般の干し柿を水分25~30%と分類しています。保存する環境によってばらつきがありますので、あくまで目安...... 続きを読む
あんぽ柿の分類と特徴 一般に市販されているあんぽ柿は渋柿を硫黄で燻蒸して乾燥させる独特の製法で作られる。あんぽ柿は、鮮やかなオレンジ色が特徴で、水分率は50%と水分をたっぷり含んでいます。食感はゼリーのようにソフトで力があり柔らかく、甘みが強いのが特徴です。 また多くの干し柿は水分が25~30%と固くなり保存性が高い特徴があり一般に、ころ柿と呼ばれます。時間が経過すると糖分の粉を白く吹く「ころ柿」などと呼ばれる干し柿となります。 ...... 続きを読む
干し柿の分類は大きく2つ 干し柿には、大きく分けて「あんぽ柿」と「ころ柿」と呼ばれるものがあります。「あんぽ柿」は水分が50%前後含まれていて、ごく軟らかめの食感を持ち、表面には白い粉がないのが特徴です。 あんぽ柿は干し柿の製法のことを指します。品種ではありません。柿の種類は峰屋柿などの大き目の柿を使い、多くは福島県などで作られています。 あんぽ柿は、渋柿を硫黄で燻製した干し柿で、ドライフルーツの一種です。福島...... 続きを読む
さくらんぼは果実のこと 一般的に「桜桃(おうとう)」は果実を含めた樹全体を表し、「さくらんぼ」は桜桃になる果実を表します。諸説ありますが、「さくらんぼ」は、赤ん坊と同じように可愛らしい様子を表現したとも言われています。 「さくらんぼ坊や」というイメージもありますから、桜桃の木に成る実を「さくらんぼ」と愛らしさを込めて表現し始めたものと想像できます。山形の生産者の皆さんは、さくらんぼのことを通常「桜桃」「おうとう」「おっと」と呼ぶことが多...... 続きを読む
サンふじとふじりんごの違いは サンふじとふじりんご、よく聞く言葉ですが、正確にはよく知られていないのが現実です。りんごの栽培過程でふじに袋掛けをして育てているかどうかで呼び方が違います。 袋を掛けずに太陽をいっぱい浴びて育てたふじを「サンふじ」、袋を掛けて育てたふじを「ふじ」と分けています。 長野県では「サンふじ」が主流で、この「サンふじ」という呼び方は、JA全農長野が1983年に商標登録をしました。秋の果物「りんご」の王様といわれる「...... 続きを読む
南水は長野県生まれの和梨 和梨の「南水」は、長野県で誕生した赤梨です。1973年に「越後」と「新水」を交配し、1990年に品種登録されました。山形でも最近、生産が増加、出荷も増えています。 南水は、長野県で生まれた比較的新しい品種の梨です。山形県では収穫期が10月上旬から中旬にかけての中生種、ちょうど豊水の収穫期、あきづきの収穫の始まりと同じころになります。 山形県では主力の幸水が終わり、次の時期に収穫される中...... 続きを読む
秀玉しゅうぎょく 特徴と形状 秀玉の栽培は無袋では果面にさびが発生しやすいですが、袋架けた栽培にしても「二十世紀」ほど外観はきれいに仕上がりません。栽培が難しい品種です。果実の大きさは「豊水」程度で約400g、甘味は多く、酸味は少ないです。渋味はなく、香気がわずかに感じられ、「幸水」や「豊水」程度の果実品質を持っています。 収穫期に入ってからの後期落果が多く見られる年がありますが、落果防止剤の利用により回避が可能です。関東で9月上旬に成...... 続きを読む
和梨 洋なしの見た目の特徴から 日本では洋梨より、和梨が最も多く生産されています。洋梨(西洋梨)はヨーロッパ原産の果実です。和梨と洋梨の最も大きな違いは、形です。 特徴的なのはその形で日本の梨が丸い形なのに対して、西洋梨は上が細くお尻が大きい円錐形のひょうたんのような形をしています。 和梨、洋なしの美味しさの違いはどうなのか、洋梨(ようなし)と和梨は、ともに梨の仲間でありながら、外観、食感、味、栽培方法などに関していくつかの違...... 続きを読む
和梨は外見で見分けられます おいしい和梨を選ぶときは、形、果皮の状態、重み、色、傷の有無などをチェックしましょう。形は、縦長よりも横に広く張りのある形の梨、すわりのいい形の梨の方がみずみずしく水分が多く美味しいとされます。 和梨の果皮は、張りがあり、色ムラがなく、傷がないものがよいです。重みは、同じ大きさならずっしり感のある重いものがジューシーでおいしい傾向にあります。青梨の二十世紀梨は完熟すると皮が黄緑色から黄色になります。傷の有無を...... 続きを読む
和梨の保存方法について 保存の基本は、水分を保つこと。5℃~10℃の低温で温度変化を出さないで保存することです。ですから、特に外気が暑い時は、できるだけ冷蔵庫の開閉も少なくできるとより効果的です。 和梨は、冷蔵保存するのが最も日持ちします。 冷蔵保存する場合は、以下の手順で保存します。 1,和梨を洗わずにキッチンペーパーで包みます。 2,キッチンペーパーで包んだあと、食品用ラップで包みます。 ...... 続きを読む
亀の尾 誕生の物語から 明治26年(1893年)は大凶作の年であった。この年の9月29日、東田川郡庄内町肝煎(旧立谷沢村地内)中村集落にある熊谷神社に参詣の折、近くの水田の水口(みなくち)に植えられていた「惣兵衛早生」という品種でした。 水の取り入れ口近くの水口に植える冷立稲の中に倒伏しないで、たわわに結実した稲穂三本が亀治の目にとまった。その三本の稲穂をもらい受け、抜き取って持ち帰ったとされます。亀治は、翌年からささやかな試験田で四年...... 続きを読む
亀の尾 美味しいお米のご先祖 現在活躍している美味しいお米の銘柄、コシヒカリ、ササニシキ、ひとめぼれ、はえぬき、山形のつや姫、などほとんどはその血統に濃い薄いの違いあれど、遡ると同じルーツに辿り着きます。 美味しいお米の源流は「亀の尾」という山形県で生まれたご先祖様です。山形県では、誕生から昭和3年までの20年間、亀の尾が作付品種としてトップに君臨していました。 [caption id="attachment_...... 続きを読む
亀の尾 現代に活躍する 近年、「亀ノ尾」種は酒米として優れていることが認められ、山形県庄内町の鯉川酒造(株)が力を入れ栽培まで取り組んだこともあり、全国三十数社の酒蔵で大吟醸酒などの原料米(酒米)として利用され、優れた酒米として称賛されるようになりました。 しかし、亀の尾は本来、現在の良質銘柄米の代表的な「コシヒカリ」「ササニシキ」「はえぬき」などは、「亀ノ尾」種のDNA(遺伝子)を持ちこれらの良質米のルーツをたどると、その元祖はすべて...... 続きを読む