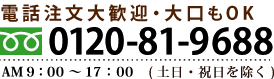さくらんぼ の作柄予想 4月下旬頃に満開になって、お天気に恵まれ蜜蜂、マメコバチに授粉を助けてもらい出来た実が育ってきています。ほぼ満開から20日が経つのでサクランボの生理落果は終わったのでそろそろ摘果作業に入らないといけない時期になりました。 生産者の小座間さんに伺うと、今年は実が付き過ぎの傾向で、多過ぎると実が大きくならないので適当な数に制限しないと品質が低下するので摘果という間引き作業をしているということです。園地を見渡すと紅秀峰の実がしっか...... 続きを読む
くだもの歳時記
白い花で満開になったサクランボの畑は桜(ソメイヨシノ)とは違った妖艶な印象が感じられます。そして畑いちめんに甘いサクランボの香りがかすかに漂っています。ようく見るとミツバチやマメコバチが活発に蜜を集めに働いて飛び回っています。 さくらんぼ受精には別品種が 今年のサクランボ、佐藤錦は昨年より2-3日早く満開を迎えました。今年が暖冬だったことと、4月のこれまでのお天気が順調で温かい気温が続いたことが要因に挙げられます。 ...... 続きを読む
さくらんぼの生育は順調 山形県の今年の桜(ソメイヨシノ)は毎年県内でいちばん開花の早い山形市の霞城公園のソメイヨシノがほぼ満開になっているほか県内各地の桜は今週末4月20日くらいに満開と思われます。さて気になるのはサクランボの開花ですが、ソメイヨシノより約1週間から10日遅れで開花するのが平年のサクランボです。ですから佐藤錦で4月下旬頃と見られています。 今年は暖冬だったこともあり平年より8日位早いという生育状況とのことです。あんまり開花が早いと、...... 続きを読む
「紅てまり」の大粒はギフト用 佐藤錦と紅てまりを中心にサクランボ栽培をしている芦野さんのさくらんぼ園には特徴があって、さくらんぼの栽培面積は60アールと決して広い方ではないが、品質にこだわった高級品だけをねらった集約的な栽培方法をしています。よそにはない高品質で鏡詰め、手詰めなどのギフト用の高付加価値の商品に絞った果樹園経営が特徴となります。 もともとサクランボは高級品ですが、その中でも芦野さんのサクランボ園では、より粒...... 続きを読む
芽欠きは実の数制限 大粒に 雪の中での剪定作業が終る2月に入ると、さくらんぼ畑では芽欠き作業が始まります。そのままにしておくと、たくさんの実が成るので自ずと小さい実になってしまうからギフト用の大粒で立派な実にするためには、「芽欠き」作業という手間をかけます。つぼみ、芽のうちからの間引き作業です。 大粒の佐藤錦などの「大粒さくらんぼ」をつくるために1本の樹につける着果数を制限します。花芽(はなめ)の中には、3-4個の花(さくらんぼの実...... 続きを読む
ササニシキ忘れられた品種 「ササニシキ」かつてはコシヒカリとともに両横綱と呼ばれた人気品種でしたが、最近店頭からは姿を消した銘柄といえます。ササニシキに替わって店頭にはコシヒカリ系の新品種(ひとめぼれ、あきたこまちなど)が多く見られるようになりました。 コシヒカリはしっかりとした歯ごたえでもっちり感があり自体の味も濃くしっかりしています。それに対してササニシキは粘りは少なくもちもち感は感じられません。さっぱりした口当たりで食味はうす...... 続きを読む
雪に埋もれた温室に蜜蜂が飛ぶ 積雪がピークに達した2月の上旬頃になると雪に埋まったサクランボの温室から何やらにぎやかな声が聞こえてきます。この頃はまだ日が短いので、一日の作業を早めに切り上げて親類知人を集めてサクランボのお花見がはじまります。温室内はサクランボの白い花が満開になっています。 積雪がいちばん多くなるこの頃、外はマイナス3℃,積雪1メートルほど温室の中は15℃前後となっていますが体感は暖かい。凍りついた外とこの環境には大...... 続きを読む
伝統のもち米デワノモチ 庄内産 「でわのもち」は全国的には知名度も低く市場流通もしない「もち米」です。長年、いろんな品種を栽培してきたベテラン生産者は「でわのもち」の品質の良さ、お餅にした時の美味しさをよく知っています。 しかし、倒伏しやすいなど栽培の難しさや収穫量が格段に低いことで販売用には作りたがらないという事情があります。「でわのもち」は天候には敏感で、非常に弱い品種なので、苦労の割に報われない品種として栽培面積と生産農家は激...... 続きを読む
こうとく香りも味も皮ごと 皆さんはリンゴを食べるとき、皮をむきますか? 皮ごと食べますか? 何故おすすめなのかというと、皮ごと食べると美味しく皮が薄くて食べやすいリンゴその上、蜜入りの素晴らしく特に香りが強い品種こうとくです。 今日は、皆さまに健康とリンゴの有効成分が一番多く含まれている皮ごと食べていただきたい一味違うリンゴ「こうとく」のご紹介をさせてください。 実は「こうとく」の果実の大きさ2...... 続きを読む
ラフランスは緑系と金系が ラフランスといえば緑色の洋梨で豊かな香りと滑らかな食感、果汁たっぷりで「洋梨の女王」と呼ばれるにふさわしい山形の特産品といえます。 実は、ラ・フランスの色には緑系と茶色系の2種類あります。通常流通されているものが緑系のラフランスです。茶色のものは通称「金系ラフランス」ゴールドラフランスと呼ばれ、昭和30年代に山形県園芸試験場 で枝変わり(突然変異)として発見されたものといわれています。 &...... 続きを読む
ふじりんご蜜入りの見極め りんごは果皮が赤く染まり、軸が太くて果皮に張りとツヤがあるもの選びます。お尻の部分は美味しさを見極めるにはとても重要なポイントです。 お尻がとんがっているものや緑色のものは未熟傾向で、お尻が丸みを帯びているもの、オレンジ色、黄色いものは完熟して蜜が入りやすく甘味があるといわれます。 またサイズは大きすぎるものよりも中くらいのほうがよく、持ったとき大きさ以上にズッシリ...... 続きを読む
市場評価が低く埋もれた品種 「こうとく」は全面に蜜が入り、食味、香りが高いりんごとして評価が高くなってきました。一方、「着色が悪く小玉リンゴ」として長い間、決定的に市場から低く評価され下積み期間を余儀なくされました。主流のサンふじに比べると格段に評価は低いリンゴでした。 そして、ようやく日の目を見るようになった苦労人の実力派の「こうとく」はこれまで誰にも知られず「まぼろしのリンゴ」として水面下に30年以上埋もれてきた存在...... 続きを読む
庄内藩士 開墾の情熱と庄内柿 さて、今回は庄内藩士の開墾に始まる柿のお話です。時代はずっと遡り幕末から明治に代わる頃の庄内藩の顛末になります。当時、徳川譜代の庄内藩は賊軍と呼ばれ、江戸を落ち会津、米沢と共に戊申戦争を最後まで戦い恭順して終ります。藩主の謹慎、公地没収などの処分を受ける中、明治四年には廃藩置県となり、月山山麓の原野 松ヶ岡を開墾する一大事業が持ち上がります。 松ヶ岡開墾場は、明治維新直後、旧荘内藩家老菅実秀...... 続きを読む
庄内柿の誕生 庄内藩の開墾から 秋になると庄内地方のあちらこちらの家で色付き始める柿の実。甘く柔らかく、歯ごたえもしっかりした柿、子供からお年寄りまでみんなが大好きな『庄内柿』です。この『庄内柿』は明治18年、偶然に紛れ込んだ1本の柿の木から始まりました。 そして、この種のない不思議な柿の木の将来性を感じ取った元庄内藩士、酒井調良が苗木を育成し普及に励んだことが、今日の庄内の秋を代表する果物『庄内柿』を生み出したのです。...... 続きを読む
庄内柿は別名 調良柿と呼ばれ 種のない不思議な柿を見つけた酒井調良は、明治26年、西田川郡黒森村(現在の酒田市)に果樹園を作り、その柿の苗木育成に挑戦します。その果樹園は、晩年の調良の号ともなる『好菓園』という名で呼ばれました。 調良はこの果樹園で接ぎ木を繰り返すことによって本数を増やし、明治30年ころには苗木の分譲ができるようになるまで栽培し続けました。この柿の木の将来性を信じていた調良は庄内地方の各地...... 続きを読む
だだちゃ豆の茹で方を復習 だだちゃ豆の知名度が高まってきたこともあり、いろいろなかたちで食べられるようになってきました。私たち生産者にとってはとてもうれしいことです。たとえば「だだちゃ豆アイス」、「だだちゃ豆まんじゅう」、「だだちゃ豆のドライフーズ」など加工品はお土産ばかりでなく一般食品や機能性の研究にもみられるようになり可能性の深堀がされ始めました。 しかし基本が大事、だだちゃ豆は鮮度が命です。朝採れしただだちゃ豆を出来るだけ早く...... 続きを読む
山形の気候が山梨と似ている 何故、勝沼がぶどうの産地になったのかといういうと、気候が適しているのは、雨の降り方が少ないことと朝晩の温度格差が大きい事が要因と考えられます。これは高い山々の囲まれた盆地であることが関連しています。そして土壌によるものが大きいのではないでしょうか。 山梨のぶどう産地は扇状地が多く砂地で水捌けが良く、標高が高い山々に囲まれた盆地のため昼夜の温度格差が大きく、日照時間が多く、傾斜地であることが葡萄という作物に...... 続きを読む
和梨産地のブランド刈屋梨 山形県では、和梨栽培は古くから行われ、130年以上の歴史を誇る。産地はいくつかあるが、「刈屋のなし」を抜きにしては語れない。ところが現在、「刈屋」という地名は、正式な住所としてどこを探しても見つからなくなってしまった。 「ここから近い、畑になっている辺りが、昔は『刈屋』という地名だったんだ」とは、酒田市の北部、旧本楯村豊川地区の生産者。「この辺は鳥海山の恵みのおかげでね。日向川が、鳥海山のブナの...... 続きを読む
昼は猛暑で夜涼しい温度格差が 桃は温暖な気候を好む作物なので大産地では山形県がほぼ北限となります。ところが、この北限の桃が、その完成度の高さで評判になっており、品質、生産量ともに全国でも5本の指に数えられます。 北限の桃だけにゆっくり、じっくり育つことが「果肉の締まり、ツルっとしたきめ細かさ」に大きな影響しているとみられます。山形の桃の畑に行くと、ふわっと甘くかぐわしい桃の匂いが鼻をくすぐる。まさに天然のアロマセラピーそ...... 続きを読む
だだちゃ豆 名前の由来から だだちゃ豆の「だだちゃ」の意味とか由来とかのお話になると必ずたどりつくこのお話し。お陰様でだだちゃ豆は人気と共に、多くの皆様にだだちゃ豆を知っていただけることになった昨今ですが、改めてお伝えしておきたいと思います。 だだちゃ豆の「だだちゃ」とは、山形県庄内地方の方言で「親父」「お父さん」という意味です。その昔、庄内藩、鶴岡の殿様が大変な枝豆好きで、毎日枝豆を持ち寄らせては「今日はどこのだだちゃ...... 続きを読む