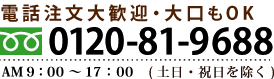さくらんぼの双子果は今年多い
5月、寒河江市の園地で、高品質なサクランボの出荷に向けたキャラバンの出発式が行われ、山形県やJAの担当者など約30人が参加した式では、サクランボの生育状況の確認や、実を落とす摘果の実演が行われ対策が丁寧に説明されました。
山形県によると、今年は4月の開花時期に晴れて気温が高い日が多かったため、サクランボの生育は平年より5日~7日ほど早く、霜による被害は少なく推移しました。しかし、今年は生産者を悩ませる「双子果問題」が実は起きていました。
確認できたのが5月の上旬、6月上旬から露地物の出荷を迎えるサクランボについて、今年は霜の被害はほとんどなかったが、異常に「双子果が多い」という問題が表面化して、山形県やJAでは、出荷量を保つため早めの摘果を呼びかけています。

前年花芽形成期7₋8月に猛暑が原因のサクランボ双子果
さくらんぼの雌しべが2つに
サクランボの双子が実る理由は前年の乾燥などのストレスが原因と言われています。サクランボの花芽が作られるのは夏、昨年の猛暑でめしべが2つに分かれる異常が多く発生しました。 春にそのめしべが受粉し実をつけたことによって、出荷することができない双子果が多くなっているということになりました。
「双子果」とは実が2つくっついて生育するさくらんぼのことです。 前の年の気温が影響していると言われ、さくらんぼの花は通常は雌しべが1つなのですが、双子果になるものは、花が咲いた時点で雌しべが2つあります。二つの雌しべが受紛して双子さくらんぼが生れたのです。
6月に迫った収穫期までにできる対策は、双子果をすべて摘果し取り去ってしますことです。この時期は収穫期を前に、通常の摘果、葉摘み、雨除けハウスのビニール架けなど収穫期をにらんでの繁忙期であり、双子果の除去という追加の作業が重く作業にのしかかってきます。

さくらんぼ摘果は実の数を少なく実を大きくする作業
双子果になるメカニズムとは
サクランボの花芽が作られるのは実がなる前の年の7₋8月の夏でこの時の天候が大きな影響を与えています。去年は特に全国的な猛暑でストレスを受けためしべが2つに分かれる異常が多く花芽に発生していたことになります。
春になってさくらんぼの花が満開になり、受粉のタイミングで、そのめしべが受粉し実をつけたことによって、出荷することができない双子果が多くなっているということになります。
園地によっては、なっている実のほとんどが双子果という枝もあり、出荷量が低下する恐れがあります。特に多い品種は紅秀峰や紅てまり等の晩生種、佐藤錦や新品種のやまがた紅王は比較的少ないというものの、品種全般に、例年より双子果が多い状況ということです。
この双子果のメカニズムとしては、猛暑や乾燥によるストレスが大きな原因。さくらんぼの樹にとって命に関わる大問題問と受け止め、我が身の危険を察知して翌年多くの子孫を残そうと双子のサクランボを実らそうという命の仕組みがあります。
対策としては、花芽が出来る7月から8月のこの時期の猛暑と乾燥に関する対応策が必要です。さくらんぼ園地をできるだけ涼しくするための工夫は限度がありますが、水を切らさないように気をつけることで。双子果サクランボの発生を少しは減らすことができるようです。

5月下旬はさくらんぼ雨除けハウスの設置作業をする
さくらんぼ双子果の対策は
去年の猛暑の影響で、今年はめしべが2つに分かれることで発生する双子果の割合が多い。県はこの双子果を収穫前の忙しい時期ですが、人の手でできるだけ早めに適切に摘果するよう呼びかけています。
少し専門的に説明すると、双子果については、前年夏の花芽分化時にめしべの基となる組織、いわゆる雌ずい原基(雌しべ)が 2 本生じること(二雌ずい形成)に起因します。この二雌ずい形成は花芽分化期の高温により発生することや、植物ホルモンのエチレンが関わっていることなどを明らかにしてきました。
これをもとに、夏季の遮光や促成栽培による花芽分化期の樹体の高温遭遇回避による二雌ずい花(双子果)の発生抑制について検討しています。おいしいサクランボを消費者に届けるために、品質の高いものを作ってもらうことが大事。摘果をしっかりしていただいて、大玉のサクランボを作ってもらうことをお願いしたい
栄養を行き渡らせ品質のいいサクランボを出荷するため、山形県で収穫前のできるだけ早時期には双子果やなり過ぎた実の早めの摘果を呼びかけています。

オウトウ双子果は毎年一定数は存在するのだが
遮光して温度を下げる工夫
- 遮光処理の試験は、光環境が良好な鉢植えのオウトウ樹での結果である。また、遮光することにより、耐凍性の低下、花芽の充実不足および結実不良への影響が懸念されるが、70%程度の遮光では冬季の凍害発生(-20℃8hr処理)、花芽および結実への悪影響がないことが確認されています。ただし、地植えの成木樹に対して遮光処理する場合は、樹冠内の光環境に留意することとしています。
- がく片形成から雄ずい形成期までの花芽分化は年次変動が大きく、山形県におけるこの分化ステージはおおよそ7月中旬から9月上旬頃の間で変動していることから、遮光処理は収穫後の7月中旬から9月上旬頃までの期間が望ましいこと。また、地域によっても花芽分化期が異なることから、花芽分化ステージに合わせた遮光が必要である。
- 遮光により葉色が濃くなり、早期落葉を防止できる。
猛暑の夏に潅水して乾燥を防ぎ果樹のストレスを低減する方法は実用化のハードルは高くないが、遮光による温度を下げる方法は、今のところ試験栽培であり、確実で現実的解決につながる方法は実用化にまだ時間が必要です。

さくらんぼの双子果は花芽形成期のストレスが原因か
双子果は核果類に多くみられる
核果類 Stone fruits. 核果類とは、ばら科のサクラ属(Prunus)に属する大木で生産される果実及び温暖な気候で生産される核果様の果実を収穫するものを指します。
桜桃(オウトウ:さくらんぼ)やスモモ、桃などのいわゆるバラ科サクラ属果。簡単にいうと大きな種を持った果物類を核果類といいます。
各研究機関や大学の研究機関では、果樹の結実性の向上を目的とした一連の研究に取り組んでいます。栽培地域や収穫時期、収穫量の拡大のため、環境や生長調節物質が生殖や発育生理に与える影響を分析したり、環境適応性を有する遺伝資源の探索と育種への利用を行ったりしています。
桜桃の一種である甘果桜桃は、暖地で栽培すると結実不良が生じやすく、双子果と呼ばれる奇形果が多く発生するという問題があります。結実不良に関しては、開花時期である春に気温が高いと胚珠が発育不良となること、そして植物ホルモンのジベレリンが発育不良に関係していることを発見しています。
▼さくらんぼ摘果作業とは