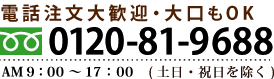芽欠きは実の数制限 大粒に
雪の中での剪定作業が終る2月に入ると、さくらんぼ畑では芽欠き作業が始まります。そのままにしておくと、たくさんの実が成るので自ずと小さい実になってしまうからギフト用の大粒で立派な実にするためには、「芽欠き」作業という手間をかけます。つぼみ、芽のうちからの間引き作業です。
大粒の佐藤錦などの「大粒さくらんぼ」をつくるために1本の樹につける着果数を制限します。花芽(はなめ)の中には、3-4個の花(さくらんぼの実)が入っていることになります。
1個の花芽に、3粒の「さくらんぼ」が、着くとして3個の花芽で 最大9粒の「さくらんぼの実」が、つくことになります。ひとつの花そう(ひとつの葉芽に6-8個の花芽ついている芽の集まり)に8-9粒の「さくらんぼ」をつけるのが、大粒の「さくらんぼ」をつくるコツということになります。

まん中の芽は葉っぱに外側に2‐3個残して全部、芽欠
大粒さくらんぼ 芽欠きが必須
大粒さくらんぼ作りには芽欠き作業は欠かせません。それは一本の樹の約60%の花芽(つぼみ)を全て取ってしまうことになります。というと簡単なお話のようですが、1本の樹に何万という蕾(つぼみ)芽が着いているわけですから、1本の樹についている小さなサクランボの芽を一定の数だけを残して全部取除くのはものすごい作業になります。
大粒のさくらんぼをつくるためには2月中旬から蕾の状態のときに、花芽が出ている段階で芽欠き(めかき)という地道な作業をしなければなりません。それは、さくらんぼの花咲くはるか前、剪定作業を終えるとすぐのまだ積雪のある2月頃からの厳寒期の作業です。
「芽欠き」とはさくらんぼの粒を大きくするために1本の樹になるサクランボの実の数を制限することで実の粒の大きさを伸ばす。それは蕾になっている花芽を一つ一つ除去していく作業をいい、蕾(つぼみ)を間引く作業なのです。
具体的には通常8個ある蕾を2個残してのこりを間引きます。遅霜の害にあいやすい所は3個残すこともありますが、通常、小座間さんの場合は佐藤錦は大粒にするために2個残します。2月の雪の残る寒さの中、根気のいる作業で1本の樹に無数にある芽を全てこのようにするには気の遠くなるような作業となります。

花が沢山集まった1花そうに何個の実を着けるか
大粒にする佐藤錦の芽欠き
生産者の阿部さんに佐藤錦を大粒にするための「芽欠き」の仕方をお聞きしました。今日の作業では、真ん中の芽を残して周りの芽を2~3個残します。今回は3個残しました。
サクランボを大粒にするためにさくらんぼの芽を3個残して取り除きます。佐藤錦、紅秀峰、紅てまり。目的はもちろん大粒さくらんぼをつくるために雪のある2月~4月までサクランボの花が満開になる直前までおこないます。
しかし、霜の被害が怖いので、芽欠きは大粒の芽から順に欠いて小さい芽を3個残すようにします。つまり芽が大きいほど早く成長するので、霜に合いにくい遅い芽を残して安全を図るのです。サクランボ霜害とは4月の開花前の蕾の時に霜に会うと雌しべが枯死して着果しなくなる害をいいます。つまりこの時期をすぎないと最終的に着果数が確定できません。
大粒の佐藤錦をつくる作業はこれで出来上がりではありません。この後も5月中旬に佐藤錦の実の数が決まったら摘果というもう一度今度は着いた実を間引く「摘果作業」をおこないます。その後また粒を大きくするために太陽光をしっかりとりこめるように5月下旬から葉摘みと作業をしてようやく6月下旬の収穫に入るのです。

想像以上に寒い時から根気いる作業の積み重ね
雪中の地道な作業が大粒に
この作業をすべての樹、すべての枝にある芽に対してやっていきますが、時間と作業量は膨大なものなるのは覚悟しなければなりません。時に芽欠き後の4月に遅霜の害で制限した芽が被害に遭うと着果数が極端に不足するという大きな被害に発展することになります。
その「芽欠き」の作業性には期限があって花の咲く前のまだ芽が固いうちに処理しないと芽がうまく取れないし、早過ぎても芽が小さくてやりにくいのです。2月から4月の開花にかけての短期間に処理しなければならない仕事なのですが出来ないと芽が大きくなって作業がしずらくても花が満開になる直前まで続きます。
寒い時期の手先の細かい作業はしっかりした防寒の身支度と手先の自由になる暖かい薄手の手袋がないとできません。寒さとの戦いが1月の剪定時から始まっています。

通常8個あるサクランボの花芽(つぼみ)を3個残す
開花受粉がうまくいかない時
この「芽欠き」作業というのはサクランボの収穫までのいちばん最初の実の制限であり膨大な作業となるわけですから大きなリスクもかかっています。この作業が終ってから大事な受粉を経て実の数が決まるわけですから、霜害や満開時のお天気が不順で受粉がうまくいかなかった場合は2倍の大きなダメージもあるわけです。
つまり芽かきは大粒のサクランボが取れるかまったく確定できない段階で、実を制限してしまうわけですから、大きなリスクを賭けることでもあるといえます。大切な受粉の時期に低温だったり、ミツバチの働きが悪かったりすると一粒も実がならないこともあります。
こうなると、芽欠きに費やしたたくさんの時間が水の泡と化してしまうわけです。このようなことも何年に1回くらいの頻度で起きますが、全部ではないので残った佐藤錦に集中していきます。
逆に受粉が順調に経過して実がなり過ぎると今度は摘果という収穫前の作業が膨大な量になってしまうので生産者は、通常、全部の樹で「芽欠き」を完全にするわけではなく、出来る範囲内の部分的に「芽欠き」して、労働力とリスクを軽減している現状もあります。

4月になって大きく膨らんできたサクランボの花芽
▼さくらんぼ芽欠き作業で大粒に
大粒の佐藤錦は芽欠きから まとめ
佐藤錦の大粒さくらんぼをねらって栽培するこの「芽欠き」で制限する方法は、芽欠きするだけでは目的の大粒サクランボになるわけではありません。
この後も5月中旬に佐藤錦の実の数が決まったら摘果というもう一度今度は着いた実を間引く「摘果作業」をおこないます。その後また粒を大きくするために太陽光をしっかりとりこめるように5月下旬から葉摘みと作業をしてようやく6月下旬の収穫に入るのです。
長年の畑の土作りからはじまり有機肥料だけを使ってサクランボの樹の栄養状態をしっかり管理しています。芽欠き作業ばかりでなく、このような、いきとどいた栽培管理を一年間油断なく丹精込めないと本当の意味で大粒さくらんぼの一級品は出来ないと小座間さんは語ってくれました。
サクランボの満開が終り、開花不粉が終れば、実の着き具合を良く観て「摘果」をして、サクランボの実に陽が当たるように「葉摘み」もしっかして収穫をむかえます。
春の3月はまだ始まり、たくさんの作業を重ねてはじめて目標に近づくことができるといえます。6月下旬からの収穫というゴールに向かって長い道のりが続きます。
そして、大事なのは日々の観察からくる毎日の管理作業があってはじめて実現すること。そして「家族の協力体制、その力が大きいですね」と生産者は語っています。